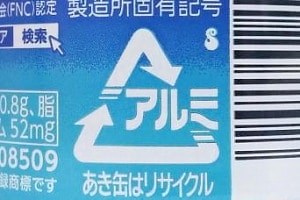覚えておくと便利 鉄の比重は7.8
鉄 Feは原子番号26、すなわち陽子の数が26の、比重が7.8程度の金属元素です。
もっとも身近にある元素なので、普通の人なら、鉄(鉄鋼)製品の重さの感覚をわかっているはずでしょうが、鉄のかたまりは意外に重く、10cm角の重量は約8kgにもなります。
例えば、アルミニウムの比重は2.7程度と、鉄の1/3程度ですから、フライパンを持つときに、アルミ製のフライパンより鉄製の中華鍋は重たいことを体が覚えていますね。

10㎜角の金属のキューブが販売されています。高価なものもあるのですが大人の趣味にどうでしょう
![]()
この鉄の比重7.8を基準に、それより密度の高い金属を「重金属」、軽いものを「軽金属」という分け方もあります。(この分類以外にも分け方があり、一つの分け方です)
核融合が行き着く先は「鉄」
太陽系を構成する元素のほとんどが水素で、それが長い年月をかけて凝集して星ができて、星の内部で核融合反応がおこり、原子番号1の水素が2のヘリウムになり、3のリチウムができて… というように、核融合によって新しい元素が生まれてきました。(もちろんこんな簡単ではないのですが、イメージです ……)
そして、その核融合の「なれのはて」が鉄Feで、核融合では、それ以上の反応が進まないといいます。
鉄以上の原子量の大きい元素は、核融合ではなく超新星爆発の強烈な圧力で生まれたと考えられています。
また、核分裂する元素も同様で、核分裂を繰り返しながら、次第に原子番号の小さな元素に変わっていって、最終的には「鉄Feになる」と説明されています。
これは、何十億年という宇宙の時間単位のはなしですが、核融合と核分裂による結合エネルギーが一番低くて安定しているのがニッケル・鉄あたりの元素なので、最終的に鉄Feに落ち着くことになると考えられています。
鉄は最も多目的に使われる金属
地球に目を向けると、地殻(地球の表面を覆う硬い層)を構成する元素の中で、「鉄」は、酸素、ケイ素、アルミニウムに次いで多い元素で、鉄は他の元素と化合しやすく、金属単体で存在するのはほとんどありませんが、鋼(はがね:鉄と炭素などの合金)にすることで無限の使い道があります。
鋼は「焼入れして硬くなる」「焼きなましをして機械加工ができる」というように、熱処理によって機械的な性質を大きく変えることができることもあって、様々な使い方ができます。
耐食性容器や低温容器に使われるステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼)は、ニッケルNiやクロムCrを加えることで、耐食や低温特性を高めていますが、炭素量が低いほど、低温特性や耐食・耐酸化性が高まります。
純鉄は「フェライト磁石」などで用いられるように、非常に高い強磁性を示しますが、同じ低炭素であっても、ニッケルNiやクロムCrなどが入った「オーステナイト系のステンレス鋼」は常磁性で、磁石にはつきません。
 砂鉄
砂鉄
この写真は砂鉄ですが、近年はほとんどが舗装されていて、「土」というものを見る機会が減りましたが、永久磁石を舗装していない道路上でひっかきまわすと、この写真のような砂鉄がとれたものです。
鉄は、このように、形を変えて、地球上に、広く広がっている状態になっています。
鉄を使う「使い捨てカイロ」
使い捨てカイロの主成分は鉄と活性炭・・・ということを知っている人は多いでしょう。
上の写真のような鉄粉(ただし、酸化していない鉄粉でないとダメ)に、保湿剤として、食塩水に浸した活性炭やバーミキュライトを混ぜると使い捨てカイロができます。
使い捨てカイロは、鉄が水酸化鉄になるときの発熱反応を利用しています。
カイロ用の鉄粉は、微細化した(これをアトマイズといいます)酸化鉄粉を、高温で還元した「還元鉄粉」(市販されている#300程度のもの)を使います。
この還元鉄粉に食塩水をかけると発熱して、軽く100℃を越えるので、バーミキュライトや炭素粉を混ぜた混合粉をフィルター紙などに入れて、さらに、上からビニール袋をかぶせて、空気のふれ方(酸化速度)を加減しています。
【注意】還元鉄粉は、空気中においておくだけでも酸化が進み発熱しますので、非常に危険な材料です。 バーミキュライトは「ひる石」とも呼ばれていて園芸店などで販売されていますし、活性炭も入手でき、還元鉄粉も入手できるのですが、一つ間違えば事故につながるので、一般の人は、知識だけにとどめておくのが無難です。
製鉄と製鋼
「鉄」は鉄鉱石とコークスを溶鉱炉に入れてつくられていることは、ほとんどの人が知っていますが、「鉄」とは元素Feのことですから、製鉄所は、鉄を作っているのではなく、「鋼(はがね)」を作っているというのが適切です。(厳密に定義するのは難しいですね)
製鉄業とは、鉄鋼を作るための素材(銑鉄や鉄合金など)に関係する業種で、製鋼業はその素材から鉄鋼や鉄鋼製品素材を作る業種ですから、例えば最大手の製鉄所(日本製鉄やJFEなど)では、製鉄、製鋼だけではなく金属加工製品までも製造販売をしているので、(きっちりとした分類は難しいのですが) 概ね、鉄鋼の素材を作るのが製鉄で、鉄鋼を作るのが製鋼と考えておけば当たらずとも遠からずと言えます。
鉄鋼は、鉄鉱石とコークスなどを加熱して、様々な元素が化合して溶けた状態で溶鉱炉から出てきた「粗鋼」を精錬して鋼塊を作り、それを加工して様々な製品になっていきます。
一般的には、粗鋼生産量で順位をつけており、かつて日本は世界一の粗鋼生産国でしたが、2023年では、中国、インド、日本、米国 の順ですが、粗鋼生産量以外のランキングをあまり見ないのは、分類がはっきりできないという理由でしょうか。
鉄鉱石
 鉄鉱石の露天掘り
鉄鉱石の露天掘り
製鉄に使われる鉄鉱石は、鉄分の含有量が多い石でないと生産効率が悪くなります。
鉄鋼の原料になるのは赤鉄鉱、磁鉄鉱と呼ばれる種類の石で、それを採掘して、採算を取ろうとすると、写真のような露天掘りができる場所が費用的に有利です。
現状では、オーストラリア(20%)、ブラジル(22%)、中国(17%)、インド(11%)、ロシア(7%)で、世界の8割近くの鉄鉱石を算出しています。
この、オーストラリアとブラジルの鉱石は、50%以上の鉄分を含む良質のものですが、鉄鋼生産量が急増した中国の鉄鉱石は、純度が30%程度しか鉄分を含んでいない低品質ですので、よく頑張っているといえますね。
中国は、鉄鋼(粗鋼)の世界一の生産国で、国策によって急成長してきたのですが、それでも、近年はコスト高になってきたことや、他国からの「作りすぎ」に対するブーイングもあって、今後の行方が注目されています。
 JFE倉敷高炉_JFEのHPから
JFE倉敷高炉_JFEのHPから
かつて日本は世界一の粗鋼生産量を誇っていました。 しかし現在、溶鉱炉(高炉)を保有しているのは、鉄鋼会社の再編もあって、日本製鐵、JFE-HD、神戸製鋼所、日新製鋼の4社に集約されていて、ここ十年来、粗鋼生産は横ばいで、極端な増減なく推移しています。
中国やインドの粗鋼生産量が増えて、世界的には過剰供給状態ですので、国内メーカーは安価な製品では太刀打ちできないので、高張力鋼板、ケイ素鋼板などの高級鋼にシフトすることで採算性を確保しています。
鉄鋼製品は大根より安い?
少し荒っぽい計算になりますが、銑鉄1kgを製造するためには、鉄鉱石が1.5kgと石炭が500g必要で、そこから得られる鋼材は900g程度になります。
鋼材の販売価格は相場で変動しますし、近年は上昇傾向ですが、1kg100円強(普通鋼材)と非常に安価です。 それには原材料費などが半分程度かかっていいるのですが、その価格を見ると、しばしば「鉄鋼は大根より安い」と比喩されます。
鉄鋼はいろんな技術が凝縮されていることを知れば安すぎる感がありますが、世界競争に立ち向かう鉄鋼関連業従事者の皆さんの努力には感謝感謝です。
もちろん、中国の減産や地域紛争などで鉄鋼価格が急上昇するのも困りものですが、鉄鋼製品は世界の繁栄を支えていますので、感謝しつつ動向にも気にかけておきたいものです。
鋼の性質を決める合金元素
製鋼の段階で、色々な特徴を付加するために合金元素を加えたり、それらの成分量を調整をして目的の鋼が製造されます。
鋼の性質は、加える合金やその量によって変わってきます。
焼入れ性(焼入れしたときに鋼が硬く強くできるようになる性質)を増したり、強靭性(耐衝撃性など)を増すマンガン、クロム、モリブデンなどの合金元素と炭素の量を調節することで、広範囲の用途に適した鋼種がつくられています。
この性能を活かすための「熱処理」は非常に重要で、硬く強くする「焼き入れ」(JISでは「焼入れ」と書きます)や柔らかくする「焼きなまし」(同様にJISでは「焼なまし」と書きます)の他に、耐食性、耐熱、耐薬品性を高める「溶体化処理」などの鉄鋼の熱処理法があります。
また反対に、強くてねばい鋼になるのを阻害する元素(リン、硫黄、銅などの不純物や介在物や酸素など)を排除するために、近年、真空技術などを含めた「製鋼技術」が向上して、非常に不純物の少ない(清浄度の高い)鋼が作られることで、鋼の品質が非常に向上しています。
【ミニ知識】 少し専門的ですが、鉄鋼成分割合(%)は、化学で使われる容量%ではなく、「重量%」が用いられます。
0.5%炭素の鋼は、成分中に重量で0.5%の炭素が含まれるのですが、炭素Cと鉄Feの比重の違いを見ると、たくさんの炭素が鋼の中に含まれています。
さらに、鉄の%は、あえて表示されないのが普通で、また、検査成績書(ミルシート)にも、すべての元素が表示されていないのが普通です。
例えば炭素工具鋼という分類の鋼で、そこに1%の炭素を含む合金とすれば、C-Si-Mn-P-S の5元素がミルシートに表示される程度で、このうち、C-Si-Mnは鋼の性質を決める合金元素で、P-Sは不純物を示す指標として明示され、その残りが鉄(Fe)であるという見方をします。
需要先の要求がなければ、この5元素すらも表示されていないミルシートも多いのですが、検査に示されていなくても、現在の鉄鋼の品質レベルは非常に高いものです。
このように、ミルシートには書かれていなくても、実際の鋼製品の中には、様々な金属、非金属、気体などが合金の状態や混ざり込んだ状態になっていることになります。
良質の鉄スクラップは非常に貴重です
昭和年代の古い話ですが、鉄鋼にあまり詳しくない人の中には、「日本の鉄はスクラップを混ぜて作っているので品質が良くない」という人がいました。(今でもおられるかもしれません)
これはとんでもない間違いです。
リサイクルされた良質な「鉄スクラップ」があって初めて、日本の最高品質の「鋼」を作り出されているのです。
日本国内には「製鉄4社」のほかに「電炉メーカー」と呼ばれる製鋼メーカーがあります。ここでは鋼を製造するために、フェロアロイという合金鉄などの原料と鉄スクラップから非常に良質の鋼材が製造されています。
ですから、高品質の鋼を作るためには良質の「鉄スクラップ」はなくてはならないもので、鉄スクラップ業者さんは大変重要な業種です。
ちなみに、鉄のリサイクル率を見ますと、スチール缶では90%近くなっていますが、その他を含めると鉄のリサイクル率は70%強程度という数字です。
放おっておくと鉄は錆びて散逸するので、この数字を高めるのは至難ですが、年々、向上する傾向にあります。
もちろん、鉄スクラップも需要と供給によって相場が形成されており、ちょっとした国際景気動向にも左右されるのですが、資源の少ない日本は特に、リサイクル率を高める努力は忘れてはいけないでしょう。
鉄や鋼のおもしろい雑学知識
鉄鋼には強磁性のものと常磁性のものがあります
鉄製品の多くは磁石にひっつきます。つまり、ほとんどの軟鉄や鋼は、外から磁場を与えると、磁気の方向(磁気モーメント)が同じ方向に向いて強い磁性を示す「強磁性体」です。
しかし、純鉄は常温では強磁性を示しますが、温度が高くなるとキュリー点と呼ばれる温度で常磁性に変化します。(もっとも、冷えるともとの強磁性に戻ります)
また、合金を含む鋼でオーステナイト系ステンレス鋼と呼ばれるものは、常温では常磁性(磁石につかない)であり、その特徴を活かして様々な鉄鋼製品に使用されています。
強反応性
水を含む空気中では、鉄類はすぐに錆びてしまうなど、いろいろな元素と化合してその性質を変えます。
錆びる時の発熱を利用した使い捨てカイロなどがありますし、反応性を阻止するために、合金成分を調整することで、耐熱鋼や薬品などに強いステンレス鋼などが作られています。
人体の組成におけるFe
もちろん、人間の身体には大切な元素で、Wikipediaによると、70kgの人に含まれる鉄は「6g」・・・とあります。
血液中のヘモグロビンには、その2/3が含まれていて、鉄分は生命維持には不可欠なものです。
 |
|
NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬鉄(アイアン) 200粒 100日分 新品価格 |
![]()
もっとも重要な「鉄と炭素」の化合
これまでに少し説明していますが、鉄(鉄鋼)の機械的性質に最も影響するのが炭素(C)です。
鋼(鉄と炭素の合金)は2%程度までの炭素を固溶し、炭素の量によって性質の違った鋼になり、さらに合金元素が加えられて様々な特徴を持った鋼になります。
炭素量の比較的低い鋼は、適当な強さと強靭さがあるので、圧延成形されて、構造用鋼としてたくさん使用されていますし、炭素量が多くなると、それを熱処理をすると硬くなるので、様々な機械部品や工具として用いられます。
このように成分の違いと熱処理の仕方を変えると、様々な機械的・化学的性質を変えることができるのは、鉄(鉄鋼製品)の大きな特長です。
統計によれば、世界で様々な金属が使用されていますが、その金属の90%以上が鉄合金ですので、鉄は地球上では最も重要で有用な金属だといえます。
 焼入れ作業:第一鋼業(株)のHPから
焼入れ作業:第一鋼業(株)のHPから
(来歴)R5.2月に誤字脱字を含めて見直し。 R7.6月に確認